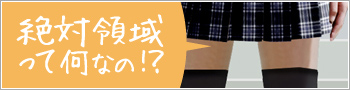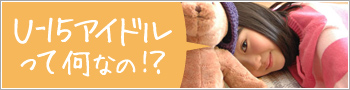元々は男女兼用だった 「スカート」
 |
| 制服のスカート (有明いく子) |
「スカート」 とは、もっぱら女性の下半身を覆うために用いられる洋装・ボトムス のひとつで、腰から下の部分に着ける布でできた筒状の外着衣服 (アウター) のことです。
元々はシンプルな構造ゆえに性別を問わず人類が衣服を身に着けるようになった頃から用いられてきましたが、中世ヨーロッパあたりからもっぱら女性が身に着けるものとして洗練され、その後ヨーロッパ式のものが他の洋服とともに広く世界中に普及するようになりました。 日本においては明治維新以降、西洋文化が入ってくる中で普及し、それまでの着物に代わり男性はズボン、女性はスカートという使い分けがされるようになっています。
ただしスカートというシンプルな服飾品は当然ながら世界中に見られ、日本でもスカートっぽいシルエットを持ち、着物の上から腰下を覆う和装の衣服として 「袴」 が存在します。 大学の卒業式などで 定番 の装いは和風スカートそのものでもあり、こちらも古墳時代から使われてきた日本独自の衣服で、元々はおおむね男性用としてのものでした。 平安時代に礼装用として貴族の間で広まり、また 巫女 などの神職や女官として働く女性も身に着けるようになります。
以降は江戸時代を通して男性の正装として用いられますが、その後明治になって活躍した女性教育者 下田歌子さんが、女官の袴を参考に女学生用の 制服 や衣服として考案し、用いるようになります。 ちなみに一般の女学生がはく袴 (行灯袴) が登場したのは1871年(明治4年) からとされています。 すなわち日本における女性用の洋装のスカートと和装の袴は、ほぼ同じ頃に広く一般化したと云えます。
丈と形状の組み合わせで、様々なスカートのスタイルが存在
スカートの分類方法は様々ありますが、おおむね筒状に作られており、筒になっておらず一枚布で腰に巻き付けるタイプは巻きスカート (マジックスカート) と呼んで区別します。 筒状のスカートの場合、継ぎ目はシームと呼び、ファスナーやポケットがついていることもあります。 それぞれ丈と形状で細かく分類するケースが多いでしょう。
丈については足首あたりまでのマキシ丈から ふくらはぎが隠れるミモレ丈あたりまでが一般に ロングスカート と呼ばれます。 膝下が隠れる程度はミディ丈、膝上までが 露出 する短いものは ミニスカート と呼びます。 極端に長いものや短いものは、スーパーロングとか超ミニみたいに呼ぶこともあります。 また全体の形状では、ウエストから裾に向かって広がる形状のものをAライン、全体に広がっているものをフレア、直線的で裾の当たりが少し広がるものを ペンシル、ボディラインに密着するものは タイト と呼びます。
一方、ウェスト部分 (ウェストライン) については、高めの位置になるのはハイライズ (股上の長さが25cm以上) でお腹を覆うようなデザインになり、逆に低めの位置になるものはローライズ (股上の長さが23cm以下)、その中間 (25cm〜23cm程度) はミドルライズあるいはミッドライズと呼びます。 ハイライズは胴が短く足が長く見える上、お腹のでっぱりもそれとなくごまかせるのでスカートの形状に依らず身に着ける際はやや上の方にもっていく事が多いでしょう。 一方で マンガ や イラスト などでは、そもそも体形を自由に描ける上にへそ出しをするためか、極端なローライズ描写も多く見られます。 実在のスカートの場合は、イベントコンパニオンやチアリーディング、あるいは コスプレ のための衣装で見られる程度かもしれません。
その他、構造的・立体的な装飾として、スカートの一部に切れ込みが入ったものをスリット、おおむね等間隔で一方向に向かって縦の折り目 (ワンウェイプリーツ (車ひだ) が入っているものを プリーツスカートやひだスカート、箱型のプリーツ (プリーツ が左右対称に折り畳まれているもの) が入り全体の折り目数も少ないことが多いものを ボックスプリーツスカート、折ひだが細かくランダムなものを ギャザー と呼びます。 またワンウェイプリーツやボックスプリーツのようなかっちりした折り目ではない、ふんわりしたものは フリル、そのスカートをフリルスカート、これらをまとめてぺプラムスカートと呼ぶこともあります (一般的には長短2つのスカートを組み合わせたような形状のものを指すことが多い)。
一方、スカート部分だけでなく ベスト や胸当てが一体化したものは ジャンパースカート (ジャンスカ)、トップス とスカートが一体化したものは ワンピース と呼びます。 ワンピースは 吊りスカート の一種ではありますが、スカート部分も持つ一枚着なので純粋なスカートとして扱われることはなく、カテゴリ としてはワンピースドレスみたいな扱いになります。 なかでも身体に密着するタイプで派手な 色・柄 と露出度の高いスカートワンピ服やスカートは ボディコン と呼ぶこともあります。 テニスなどスポーツで着用される短いスカート状のものはスコートと呼びますが、元々の意味や語源は同じです。
日本においては車ひだプリーツのあるミディ丈のスカートが学校の女子用制服としてよく用いられます。 この他、ボックスプリーツのジャンパースカートも比較的多いでしょう。 プリーツやボックスプリーツの入ったスカートは動きやすく足さばきも楽で、活動的な児童や生徒に向いているという部分があります。 トップスは セーラー や ブレザー、イートンやボレロなどでほとんどを占めます。
また時代ごとに制服の着こなしや着崩し方にも流行があり、ミニにしたりロングにしたりまたミニに戻ったりと、時代ごとにその長さに際立った違いが現れます。 1970年代から1980年代あたりまでは長めのスカートにすることが流行りましたが (いわゆるつっぱり・ヤンキー風)、1980年代後半から1990年代にかけてはミニが流行。 その後はずっとミニスカートの 覇権 が続いています。 これらは時代時代の一般向け ファッション トレンドに沿ったものですが、1990年代以降は、むしろ制服の着こなしが一般向けトレンドに影響を与えるようにもなっています。
人類の歴史とともにスカートがあり
洋風スカートの起源は古代に遡ります。 紀元前4000年頃のメソポタミア文明では、男女問わずスカート状の衣服を身に着けていたことが知られています。 素材は羊毛やリネンで、動きやすさを重視したデザインでした。 単に下半身を隠したり保護するだけでなく、様々な素材や形状・スタイルが考案されたり、装飾的な要素が加わるようにもなります。 とくに上等なものは素材や色や長さ、形状などによって、身に着ける人の階級や職業などをあらわすものでもあったようです。
ヨーロッパにおいても同様の経緯で古来よりスカートが用いられますが、男女ともに着用しつつ、もっぱら男性は短いもの (現在のミニスカートのようなもの)、女性は長いものを身に着けるといった区別はあったようです。 これは男性がより激しい動きをすることから生じた分化なのでしょうが、徐々に男性らしさや女性らしさを表現するものともなり、当時の女性が男性の逞しい足にセックスアピールを感じていたことをあらわしています。 映画や ゲーム などで見かける古代ローマ兵のタッセルなどが有名ですが、現代とは正反対ですね。
一方の女性のスカートは長く、これは身体を使った仕事をしない (おしとやか) みたいな意味もあれば、男性と異なり下半身ではなく上半身で異性に性的なアピールをすることが多かったからという理由もあります。 女性はおおむね上半身を大きく露出する服を着て、きめ細かな美しい肌、性病にかかっていない健康的な身体をアピールしていたようです。 これはその後のイブニングドレス (肩や胸元を大きく開いたロングドレス) などにも直接的な影響を与えています。 ただし豊かな胸ははしたないとされ、なるべく平らに見えるように工夫するなど、避けられる傾向があったともされます。 これは豊かな胸が魅力的であるがゆえの逆説的な禁忌なのかもしれません。
中世ヨーロッパでドレスとともに発展するスカート
一枚布を腰にまけばとりあえずは巻きスカートになりますので、現代の多様なスカートのスタイルがいつ頃発展したのかはスカートの定義にもよります。 とはいえ現在世界中の女性が身に着けている女性用スカートの直接的なルーツついては、おおむね中世ヨーロッパで発展した、もっぱらドレスの一部として扱われていたものの発展形のようです。 とりわけ貴族階級の女性たちは華麗なドレス姿を競い合い、フリルやレース、刺繍などで装飾された豪華なスカートを着用しました。 16世紀頃からはペティコートやクルーラースカートなどの 下着類 もあわせて利用されるようになり、スカートの形状にも大きな影響を与えています。
19世紀、ビクトリア朝時代となると、生活に支障をきたすほどの広がりのあるスカートが好まれ、逆にウェストは強く締め上げて細くし、女性の身体のシルエットを際立たせるようになります。 スカートをボリュームアップするために骨組みのような構造を内部に持ち (クリノリンやパニエ)、表面にはホイップルと呼ばれる豪華な飾りがつき、ウエストはコルセットで締め上げる西洋貴族の姿としておなじみのスタイルです。 これは当時の美の基準とされエスカレートし続けますが、一方で一人で着ることも脱ぐこともできないか、できても異常に時間がかかるものであり、実用性には乏しいものでした。 結果的に女性の行動が制約される原因ともなり、巨大なスカートやコルセットからの解放といった考え方も生じる事となっています。
ただしこれらの華美なファッションは上流階級のみであり、庶民あるいは人口の大半を占める農民は実用性と質素さを重視したものとなっていました。 基本的には麻や羊毛などの自然素材で作られたオーバーコートや簡素な ロングスカート、エプロンなどを着用し、頭には 髪 をまとめるためのボンネットやスカーフをかぶるのが一般的でした。
20世紀に入るとスカートは大きな変革を迎えます。 第一次世界大戦中に男性労働者が不足するようになると女性も労働市場に参加し、より実用的な服装が求められるようになりました。 その後も第二次大戦や戦後の女性の社会進出に伴い膝丈やミニスカートといった新しいスタイルが登場し、女性の解放の象徴とされました。 1958年のマリー・クワント、1965年のアンドレ・クレージュによるミニ・ルック (Mini Look) は1960年代に世界的なミニスカートブームを巻き起こし、日本でも 「ミニの女王」 とも呼ばれたツイッギーの1967年10月18日の来日を機に空前のブームが巻き起こり定着することになりました。
一方で伝統的な男性用スカートの文化が世界的に廃れる中、ユニセックス といった考え方が広がると、異性装 ではない 中性的 な、あるいは純粋な男性ファッションとしての男性用スカートも登場するようになっています。 2000年代に入ってしばらくすると、都市部のおしゃれな人が集まる街で少しずつ見かけるようにもなっています。 この場合、完全な筒状のスカートではなく、袴のような見た目がスカートっぽい形状のものもよく選ばれます。