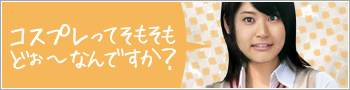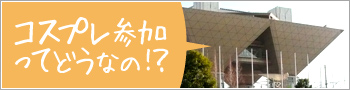ある意味伝統文化的な趣もある 「特攻服」
「特攻服」(とっこうふく) とは、暴走族やつっぱり、ヤンキー (珍走団や DQN とも) が身に着ける独特な ファッション アイテムのことです。 もっぱら男性用のものでしたが、1980年代頃からは女性 (レディース) も着用するようになり、略して 「とっぷく」 になったり、「纏」(まとい) と呼ぶこともあります。 足元は ブーツ が 定番 というイメージがあり、これはバイク (単車) に乗る際に裾が邪魔にならないようにするためですが (単なる長靴の場合もあり)、元々さほど多くなく、また時代を経るごとに減りつつあります。
多くの場合、文字 (漢字表記で定番の フレーズ 「天上天下唯我独尊」「喧嘩上等」「天下無敵」「国士無双」「暴走天使」「只今参上」「命短し恋せよ乙女」 や漢字当て字のチーム名、詩などが多い) と 図案 (菊のご紋、龍や虎、桜、薔薇、花札、般若といったものが多い) などの飾りが刺繍で施されています。 暴走族の集会 (走行会) に参加する際に着用するほか、学校 の卒業式や地域のお祭り、成人式の他、何らかの イベント など、特別な日に揃って身に着けて記念にしたりします。
暴走族のチームによっては腕っぷしが強くバイクなどの運転も上手で肝が据わった 精鋭 メンバーで構成される特攻隊や親衛隊、切り込み隊、あるいはチームのリーダー (頭・ヘッド) のみに着用を許すといった決まりがある場合もあります。 これらの人たちは走行会の際にとくに危険な役割をするメンバーであり (赤信号や検問に真っ先に突っ込んで本隊のための血路を開く、ケツ持ち (殿 (しんがり) として最後尾について本隊を逃がす、敵対チームとぶつかったら切り込む)、単に見栄やプライドのための着用という訳ではなく、夜道の暴走でひときわ目立つことが役割上求められているという部分があります。
当初は先輩から後輩へ受け継がれることもありましたが、主に刺繍が安価になったこと、ヤンキー向けの若者雑誌などが登場し第三者に見せる機会が増えたこともあり、後年は比較的自由に新調して着用するようにもなっています。 それ以前までは、夏場は Tシャツ やアロハ、ダボシャツ、甚平、ド派手な 柄 シャツ にスイングトップやスカジャン、冬場はスウェットや ジャージ に革ジャンやスタジャン、ドカジャン、さらには本職 (ヤクザ) っぽいガチガチなスーツ姿などなど、かなり自由でした。
あまりに特徴的な衣装であり、一般人 がイメージする暴走族やヤンキーの代表的服装の一つとなりますが、現在では暴走族やヤンキーの数も減り、「本物の特攻服」 と呼べるようなものを街角で見かけることは一部地域を除けば減りました。 しかしアイドルの ライブ・コンサートなどでは、昭和時代から続くアイドル応援服として、非ヤンキーの熱心な ファン による コスプレ 的な着用も残っています。
おたく といった世界とは縁遠い人たちの服装ですが、前述したアイドルのライブやコンサートにおける応援服としての利用や、そもそもヤンキー系の マンガ にファンが少なくないこともあり、創作の際にも様々な用いられ方がされています。
作業着や戦闘服から特攻服へ
特攻服の原型となったのは工事現場の作業着や暴力団の下部構成員が事務所などに詰める際に着用していた 戦闘 のための服であり、動きやすさを重視したものです。 いわゆる旧日本軍による特攻 (神風特別攻撃隊) の際の戦闘服 (飛行服) とは何の関係もありません。 「特攻隊員が着用していた服」 ではなく、あくまで 「命を捨てるつもりで突っ込む時の服」 といった意味の名称となっています。
とはいえ旧日本軍的なテイストが全くないわけではなく、菊のご紋、日の丸や旭日旗、菊水といった意匠を取り入れたり、日の丸ハチマキといった特攻を想起するアイテムを併せて着用したり、紐や布地を和服のたすき掛けのように体に結び付ける、晒 (さらし) を腹部に巻き締める、足袋や雪駄といった和の履物と組み合わせるなど、日本風の味付けが極めて濃厚に施されている場合が多いでしょう。 ただし下半身のズボン部分には、変形学生服と同じようなボンタン (太もも部分のワタリが広く、裾を細く絞ったもの)、工事現場の作業着として用いられるニッカボッカやその形状を持ったパンツが使われる場合もあります。 その他 腕章 や マスク、サングラスなどもよく合わせられるアイテムです。
当初は色も白や黒、紺が中心で上着も短くごく 地味 なものでしたが、その後長いタイプ (コートのように羽織るもの) も登場。 これは改造された学生服 (学ラン) における長ランやその発展形である洋ランの影響ですが、長ラン自体は大学の応援団が身に着けるようになったものが発端で、その源流には旧日本軍の軍服の意匠、さらにはバンカラ (西洋かぶれのハイカラに対する蛮カラ) も含まれており、文化としては連続性があります。
ちなみになぜ長くするのかといえば、旧軍の軍服における礼装にシルエットの原型があるともされますが、端的に云えば先輩に礼 (お辞儀) をする際にお尻と背中の部分が見えたり下に着たシャツが乱れて 露出 するのを防ぐためです。 通常は合わせて首元の詰襟部分も長くしますが (ハイカラー)、こちらも先輩に礼をする時に首だけで頭を下げるのではなく上半身全体でするためだと云われていますが、丈が長いと詰襟がそのままではバランスも良くないため、後付けの理由という部分もあります (明治中頃からのハイカラ文化とも直接の関係はありません)。
特攻服にせよ学ランにせよ、上下関係にうるさく先輩からの伝統を受け継ぐ集まりならではの様式と云え、その後、長ランに代わって丈や詰襟を短くした短ランが登場すると、その影響で極端に短くした特攻服の上着なども登場しています。
色とりどりのカラフルなものも登場し、よりカジュアルに
1990年代前後となると、紫やエンジ、ピンクといったカラフルなものも登場し、あわせて刺繍も華美なものに。 元々特攻服の刺繍は、作業服や戦闘服の胸元に会社名や組の代紋を刺繍したり、背面に大きな絵柄を刺繍するスカジャンの影響からですが、刺繍が大きく華麗で数が多いというのは不良としての格を表すものでもあるので、その傾向は強まる一方となっていました。
ひと昔前の刺繍は職人が横振りミシンを使って生地に手作業で図案を起こす、とても手間と技術が必要なものでした。 当然極めて高価で、大きなお金を動かす器量や多くの後輩らから慕われているとの権勢を示すもの (後輩からのカンパ (ある種の上納金、パー券やステッカー販売のあがり)、要するに単なるファッションではなく力を誇示するためのものだったりします。 いまでは刺繍用のコンピュータミシンも広まり、定番の図案や文字刺繍などはかなり安価となったこと、そもそも暴走族やヤンキーが流行らない時代になったこともあり、こうした見栄の部分は一部を除きかなり縮小し、純然たる見た目重視になったといって良いでしょう。
なお 同人イベント などではコスプレの扱いとなりますが、ヤンキーマンガや アニメ の キャラ としての着用ならともかく、実際のヤンキーが実在する暴走族の特攻服を着て 参加 するのは難しいケースが多いでしょう。 もちろんルールを守り トラブル を起こさないのであれば、ある意味で 「趣味」 の範疇とも云え問題はないとも云えますし、過去に実例がないわけではありませんが。
地域のお祭りなどに登場する徒歩暴走族 (バイクなどに乗らず徒歩で集まって騒ぐ人たち) や、アイドル・ロック歌手のライブなどでは、周囲を威圧したり誤解を招くとして着用が禁止されていることも多く、「たかが服とは云えない」 という部分はあります。 何かとゆるい時代だった頃に咲いた消えゆく文化といった趣があります。