情報伝達したり仲間との連帯を感じたり… 「ハンドサイン」
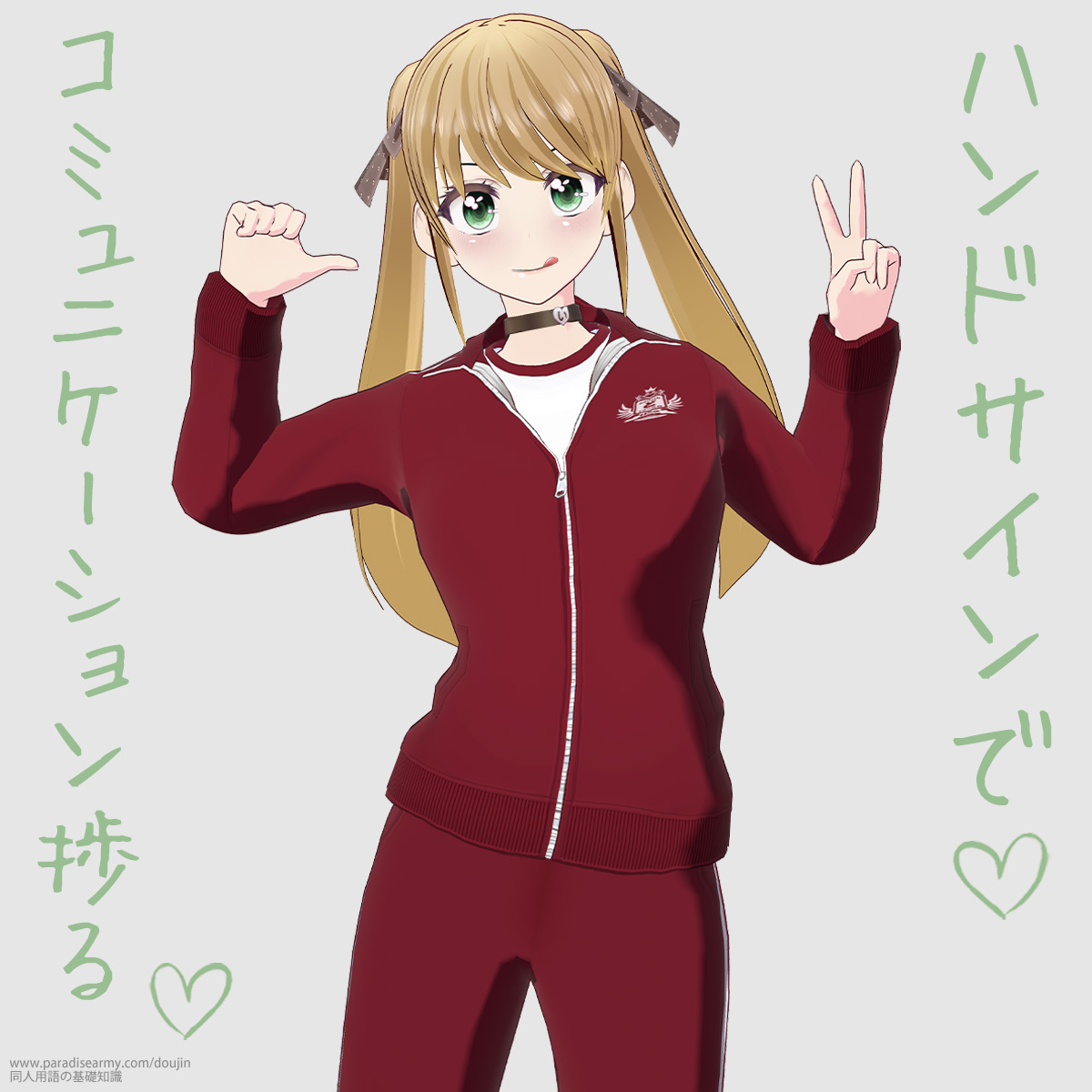 |
| ハンドサインで コミュニケーション捗る (有明いく子) |
「ハンドサイン」(hand sign) あるいはハンドシグナル、手信号とは、人間が手や指の形や動きを使って表現する、もっとも代表的なコミュニケーション手段 (共通言語・コミュール) のひとつです。 手振りやジェスチャーとも云います。
ボディランゲージの一つであり、人類が音声言語や文字を使うようになる前から存在したと思われ、古代から人類のコミュニケーション範囲の拡大や多様性に合わせ発達してきました。
使われ方は文化や時代、用途によって異なりますが、道具がいらず、また音を立てることもない上に音声に比べて到達する距離 (視認範囲) が非常に長いため、集団での狩猟や戦争などなど、複数人が周囲を警戒しながら共同で実施する作業や行動に適していたと云えます。
古代のローマやギリシャでは、演説や演劇で言葉にできないイメージや感情を身振り手振りによって補強・補足でき、それによって表現力が高まり、また説得力も高められるとされました。 有力政治家や思想家を中心に、技術としての研究や洗練もされていました。 また宗教儀式では 祈り や祝福といった特別な行為に特定の手や指の配置が定められ、その後はその形自体も神聖視されるようになっています。 日本では仏教の仏像が行う独特な印相や手印がおなじみでしょう。 仏の教えを形にしたものといえ、拝むだけで説法を聴いたのと同じ功徳があるとされます。
海事や軍事、ビジネスの場でよく用いられるハンドサイン
ハンドサインがとくに多角化し発展もしたのは近現代で、なかでも海運を中心とした海事や 軍事 の世界でしょう。 音声による伝達が難しい 環境 であり、視覚的に情報や指示を伝えるための手法として洗練されます。 統一された信号も整備され、船上や戦場で行動を統制する実用性から重用されるようになります。
これは有線・無線問わず通信技術の発達によって船舶の運航・戦場の指揮などが 現場 以外の遠隔地から行うことが増えた現代においても重視されており、習熟は最低限の条件ともなっています。 命令が伝わらなければ作戦行動ができないだけなく、そのまま生死にもかかわるだけに当然です。 実用性だけでなく儀礼用にもよく使われ、とくに右手を頭の横に添える敬礼などは、もっとも有名なハンドサインのひとつかも知れません。
また一般にも広く知られているものに、アメリカ軍の特殊部隊、SWAT の戦術的サイン (Hand Signals) があります。 様々なサインを図解で一覧表にまとめたものは度々 ネット で話題となっていますが、片手に銃を持つことからもう片方の手でのみで意思疎通が行えるよう工夫がされていて、とても分かりやすいのが特徴です。 実用性もあって同様の効果を見込めるサバゲー (サバイバルゲーム) でそのまま使われたりアレンジされて用いられたりしています。 また一覧表自体が コラージュ や パロディー の ネタ 用の素材として ネットミーム にもなっています。
この他、ビジネスの世界では市場での迅速な情報伝達のため、市場関係者らがよく使います。 またスポーツの場でのチームメイトへの指示出し (野球におけるサイン (フラッシュサイン (手で体の一部を一度触る) とブロックサイン (体のいくつかの部位を決められた順に触る) などなど、ありとあらゆる人間の営みになくてはならないものとなっています。 一部は手だけでなく身体全体を用いるもの、あるいは視認性を高めるための道具 (手旗とか) を用いることもありますが、あまり極端なものはハンドサインとは呼ばれないこともあります。
一方、極めて独特かつ重要なものに、聴覚障害者のための手話 (および指文字) があります。 文字通り手の形や動きで会話を行うためのもので、原型自体は古くからあるものの、とくに20世紀以降は完全な言語体系として整備され、語彙の組み合わせだけでなく文法も持つ独立した言語として発展しています。 近年では手話そのものが国際的に音声言語と同等のものとの扱いがされるほどの認識がされるようになっています。 すなわちコミュニケーション言語には文字、音声、そして手話 (指文字) があるというわけですね。 手の形が示す意味などは文化に強く依存する部分がありますが、それは文字や音声言語も同じです。
政治や文化の場ではシンボルとして用いられることも
ハンドサイン自体は誰でも 日常 で、ほとんど無意識に近い感覚でよく使うものでしょう。 例えば誰かに方角や対象物を指し示す際に一本指を伸ばして指差ししたり、口元に指を当てて秘密や内緒の話だと示したり、真っ直ぐ延ばした手の平を両目の目尻の位置に水平に当てて泣いたふりで悲しみを表現したり、握り拳で威圧する、親指と人差し指で輪を作って OK、親指を立てて相手を褒める (GJ) などです。 これらは後天的に獲得するものもあれば、乳幼児がほとんど感覚的に行うこともあります。 また手の基本的な形である握り拳・2本指・手の平開きはグーチョキパーとして、簡単な ゲーム で 勝ち・負け を決めるためのジャンケンにも用いられています。
ある程度の年齢となると、言葉では伝えきれない機微や ニュアンス、口にするのは憚られるようなものを、ある種の隠語のような形でハンドサインで示す行為も行われるようになります。 例えば手の平を首元に水平に重ねて横に引くことで首切り (解雇) を示したり、小指を立てて恋人、手を握って人差し指と中指の間に親指を入れて女性器、頬に人差し指で線を引いて頬傷を表現してヤクザや反社会的勢力を示したりなどです。 その他、一般的には差別表現や ヘイトスピーチ、Fワード とされるような言葉をハンドサインで代替するなども多いでしょう。
これらは指差しや握り拳のように機能性のある形や実際の行為を模した形ゆえに、ほとんどあらゆる文化圏で同様の意味や目的で使われるものがある一方、特定の職業や地域、文化圏に属する価値観を 共有 する者の間でのみ通じるものもあり、翻ってハンドサインという共通言語を持つもの同士の連帯の表明、あるいは仲間かどうかの識別にも使われるようになります。
とくに政治やサブカルチャーの文脈では、それぞれがシンボリックなハンドサインを持ち、それがある種のアイデンティティや連帯、あるいは敵意を示す表現手段として使われることが増えています。 政治運動では指の形で特定の政治勢力や団体の支持や不支持を表明したり、敵対勢力を暗示するための 犬笛 として用いることもあります。 ロックやヒップホップの ライブ などで、演者 と観客、観客同士の一体感を生むハンドサインやジェスチャーが生まれ定着しています。
1970年代から、日本ではピースサインが大流行
こうした用途でもっともポピュラーで、かつ日本でも日常生活で多用されるものは、手を握って人差し指と中指だけをV字型に伸ばす Vサインやピースサイン でしょう。 Vとピースでは使われ方も意味も異なりますが、使われる文化圏や文脈によって様々な意味を持つようになっています。
日本においては写真撮影の際の 定番 のハンドサインとなっており、両手でピースする ダブルピース や手首をひねって横倒しにした横ピース、手の平ではなく甲の部分を向ける裏ピースや逆ピース、そのまま下向きにした下向きピースなどなど様々な バリエーション が広まっています。 これらは ギャルピース と呼ばれることもあります。 この他、手でハートマークを作るとか、やや奇抜なものでは乳首を強調する よろちくび〜 などもよく行われます。
またハンドサインそのものが手話以外にも一つの言語としての役割を果たすこともあります。 例えば絵文字や手のジェスチャーを模した 図案 や アイコン が視覚的な言葉や符号としてコミュニケーションに使われたり、「ピースサイン」 や 「振り上げた拳」 といった言葉そのものが何らかの意味を持つこともあります。 ハンドサインは時代とともに拡張され続けている、人類の重要な言語のひとつと云えるのでしょう。
ただしハンドサインの意味や意味の強さは文化や文脈で変わってきますので、異なる文化圏の人や外国人に宛てて使う場合、あるいは ネット の 越境投稿 などで用いる際には注意が必要です。 あらぬ誤解から トラブル を招かないようにしましょう。 例えば中指を立てるファックサインなどは日本でも侮辱や軽蔑の意味で使われますが、欧米では日本以上の強さで 認知 され、相手や状況によっては冗談では済まなくなるケースもあります。





