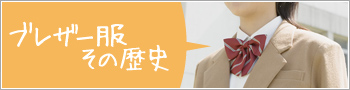凛々しさがある一方、服従と統制もある 「制服効果」
 |
| 制服を着るとやっぱ ぴりっとするよね (有明いく子) |
「制服効果」(ユニフォーム効果) とは、学校の制服 や特定の職業を象徴するような制服を身に着けることで着用した本人の心持ちが変化したり、態度や振る舞いに影響を与えること、あるいは私服姿ばかり見ていた家族や友人知人、とりわけ 幼馴染 などが、これまでとは異なる大人びて凛々しい姿に心が動かされてしまうことです。 馬子にも衣裳というやつですね。
一般的な制服効果は、ポジション効果 (置かれた立場や座るイスが人間を作る) といった意味で用いられることが多いでしょう。 それまで頼りなくだらしなくも思えた人物が、例えば警察官とか消防士といった社会的に信頼され厳格なイメージのある職業の制服を身にまとうことで見違えるように頼もしく感じられたり、本人も何やら気持ちがシャキッとし、そのイメージに沿った言動を行うようになるといったイメージです。
これらはある意味で人間にとっての極限状態でもある戦場に赴く軍服などでは、とくに顕著に感じられるものです。 尉官・左官・将校といった上級階級の軍服などは、その存在が周囲にも本人にも大きな心理的影響を与えると考えられていますし、実際に周囲のものには圧力や畏怖を、本人には自信や責任感を与えるものと理解されているようです。 制服は軍事組織に最重要な規律と服従の象徴でもありますが、ほとんどの軍隊ではそれ以上の熱意で軍服や身だしなみに拘ったりもします。 中世の武士や騎士らの華麗な甲冑などにもそのルーツは見ることができます。 戦場で目立って手柄を誇示したり、勝負服・死に装束としての精神的意味も小さくありません。
マンガ や アニメ といった創作物においても、主な 舞台 が 学校 だったり、キャラクター がそこに通う生徒・学生だったりもするため、設定 として制服姿が極めて多く、またキャラの魅力や個性を際立たせるものとして重視されます。 生徒・学生以外でも、看護師 (看護婦) が身に着けるナース服とか警察官や自衛官の制服、コンビニエンスストアの制服、その他あらゆる職業の制服や職服が、ある種の 萌え要素 としても利用されています。
ナチスドイツの制服はかっこいい…それだけに罪深いもの
制服効果をある意味でもっとも有効に活用したのは、ナチス時代のドイツでしょう。 ヒトラー率いるナチスは政権掌握前から軍服を使った統制を試みていました。 当初はナチスの私兵である突撃隊 (SA) に在庫がだぶついていたオーストリア植民地軍の熱帯地用として使われていた褐色の シャツ を購入して用いており、安価で大量に調達できたから選ばれただけだと云われていますが、心理的一体感やその強制のために役立ったとの話があります。
同じ服を着た褐色の軍団が規律正しく行進するさまは、政治的・経済的に混乱する当時のドイツにあって強さや揺るぎない意志、正しさや秩序を感じさせ、人によってはとても魅力的に見えたものなのでしょう。 ちなみにまだナチスが在野の政治団体だった頃、示威的なパフォーマンスに用いられる制服の着用が当局によって禁止されたことがあります。 その際は別の服を着るのではなく、抗議の意を込めてあえて服を脱ぎ上半身裸で行進したとの逸話もあります。
突撃隊はナチス内部の権力闘争の末に粛清などを通じて地位を追われ、その後に台頭した親衛隊 (SS) にその役割の多くを奪われますが、親衛隊生みの親の一人でもあるヒムラー独特の美意識と、それを形にした党員カール・ディーメルとヴァルター・ヘックにより、当時各国の軍服の中でも極めて洗練されたシルエットを持ち、現代にあっても人々が制服に覚える様々な意匠・イメージを体現する重要なもののひとつとなっています。 元々ドイツ国防軍の制服の評価も極めて高いのですが、ナチス将校のそれは全体のシルエットや襟の形状や 色、合わせる帽子や徽章類や 腕章、ロングブーツ などにもさらに工夫が凝らされ、より魅力的に見えるようになっています。
これらは中世のドイツ騎士団にイメージを求め、神秘主義的なルーン文字の SS マークと髑髏マーク (トーテンコップ) をあしらった漆黒の制服として広く知られています。 いずれの意匠や装飾もしょせんは子供だましのこけおどしのようなものですが、混乱する街角や極限状態の戦場では人々の深層心理や感情に働きかけ、彼らが行った 無慈悲 な非人道的行為とオーバーラップし、理屈では説明できない恐怖を与える心理的効果があったともされます。
とりわけ黒い色は当時のプロパガンダ映画の モノクロ 画面 によく映え、中世以来のドイツの軍事エリート集団のイメージを強く喚起するものでした。 将校などは支給品ではなくオーダーメイドしたものを着用し、さらに細部が異なる場合もありますが、いずれも統一感のある美しさを持っています。 これらはイタリアのファシストやムソリーニの軍服や礼装に強い影響を受けたヒトラーの美意識にも合致し、ある種の 「制服の帝国」「バラバラの個人ではなく一つの意志の元に従う集団」 といったイメージを現代に喚起するものとなっています。
ナチスドイツでは伝統的なドイツ国防軍と新設された親衛隊とで限られた優秀なドイツ人男子の奪い合いも生じており、魅力的な昇進制度や福利厚生的な各種優遇措置に加え、制服のかっこよさも志願制の時代には人材獲得にプラスに作用したともされます。 軍人と云えども一人の若い男性であり、戦時はともかく平時にあっては 「制服がかっこいい」「着ていると異性にモテる」 というのは大きな魅力です。 国家の中枢を担うナチスのエリート集団に属する人物としての証明をしつつ自らを凛々しく飾り立てるナチス親衛隊の制服は、たいそう魅力のあるものだったのでしょう。
余談ですが、数学者で大道芸人のピーター・フランクルさんが以前、とある歴史番組にコメンテーターとして登場した際に、ナチスの整然とした制服による行進を見て心が躍るし気分が高揚すると 軍靴の音 の口真似をしながら評したことがあります。 フランクルさんはハンガリー出身のユダヤ人で、両親はナチスの強制収容所の体験者で親族にも被害者がおり、彼自身は戦後生まれながらナチスの暴力を身近に感じる境遇でした。 そんな彼がいうこの コメント は、そのような制服のプロパガンダに踊らされたドイツ国民への憤りや深い悲しみ、プロパガンダの持つ恐ろしさや強い怒りを逆説的に鋭く説くものなのでしょう。
実際ナチスの記録映像などを見ると、その力強さや整然とした美しさ、勇壮な行進曲 (ニーベルンゲン行進曲やバーデンヴァイラー行進曲など) に、蛮行を知ってなお心を奪われるものがあります。 とくに1934年にレニ・リーフェンシュタール監督によって制作された記録・プロパガンダ映画 「意志の勝利」 で繰り返し映される制服の行進は、その極致といって良いでしょう。 理屈を超えた潜在意識に働きかける何らかの力さえ感じてしまいます。 それだけに罪深く、また恐ろしいものなのでしょう。
日本でも公開された映画 「ちいさな独裁者」
同じナチス関係では、第二次世界大戦末期、遺棄された軍用車の中にあった将校 (太尉) の軍服を拾って身に着けた脱走兵 (上等兵) の若者が、その制服の威光による借りものの権力で徐々に独裁者的な狂気に取りつかれ怪物化するというヴィリー・ヘロルトの事件 (1945年3月) もあります。 こちらはその後小説や映画などにもなり、日本でも公開された映画 「ちいさな独裁者」(2017年) はとくに有名でしょう。 いずれも権力とその象徴である制服が持つ魔力と恐ろしさを示すエピソードでしょう。
ちなみに親衛隊はじめナチス関連の制服のデザインに、ヒトラーが愛したドイツオペラの華麗な舞台衣装のアイデアや人材が用いられたとの話もありますが、これは後に半ば伝説化した逸話の要素が多く、また戦後 HUGO BOSS とのデザイン ブランド として頭角を現すヒューゴ・ボスのデザインによると云うのも根拠はあいまいです。 ボスが制服卸しをしていたのは事実ですから、そこから膨らませたイメージの可能性が高いのでしょう。
いずれにせよデザインとして極めて優れていたドイツ国防軍やナチス風制服は世界中で模倣され類似の意匠を持つものの枚挙にいとまがないほどです。 日本においては警察官の制服として採用されたものがその特徴を良く持っていました。 その後1994年4月1日になると、厳格な警察官といったイメージから親しみやすさへとイメージチェンジが図られ、とりわけ夏服のライトブルーのものは、アメリカの警察官制服のイメージやアイデアを活かしたものへとリニューアルされています。
制服の効用や魔力、恐ろしさをどう捉えるかは、現代にも突き付けられる大きな テーマ のひとつです。