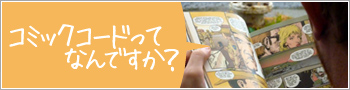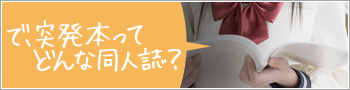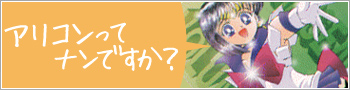邪念が渦巻いておるわ! サクラさんのセリフ 「面妖な…」 から 「Men用な本」 が…
「面妖本」(めんようぼん) とは、18歳未満禁止 の 同人誌、すなわち 「エロ同人本」(しかもしばしば 無修正同人誌) のことです。 「Men用本」 とも。 マンガ や アニメ を対象とする 同人 の世界で使われる言葉としてはわりと古い部類に入り、使われていた時代は 1980年代の前半がその中心でしょうか。
なお 「面妖」(めんよう) とは、奇怪だ、奇妙だ、不思議だ、不気味だ、ちょっとおかしい…なんて意味の昔の言葉です。 「同人誌」 と云えばマンガ批評やマンガ論、ファンサークル、ファンクラブ (FC) の会報なんかが多かった時代、二次創作 で、しかも 「エロ」、さらに ロリ なものはまだ 「避けようよ」 的な空気も依然としてあり、それにあえて踏み込んだ本を 「奇妙な本だ」「妖気が漂っている」「煩悩が詰まっている」 などとシャレで使って通じるケースが多かったのでしょう。
この頃に 「面妖本」 と呼ばれるようになった直接の語源となる具体的な出来事はありそうですが (後述)、1990年代くらいまでは、ちょこちょこと見かける 「男性向け同人誌」 の俗称のひとつでした。
男性向け同人 「特殊同人」 と 「Men用本」
この言葉のルーツとしては、1980年代、男性向け同人誌などを 「Men用本」 という隠語で表す表現があり、これが転じて面妖本となったとの話があります。
また同じころ、同人誌などの 書店委託 などを行っている 「とらのあな」 において、初期の頃にこうした本を 「特殊同人」 と呼んでいたこともあり、「それまでのファン活動の延長としての同人誌とはちょっと違う、「実用性がある同人誌」「でもエロ同人とか直接的には表現しにくい本」 の呼び方が、様々現れていた時期だったと云えるでしょう (情報ありがとうございます)。
初期の男性向け同人を強力に牽引した 「うる星やつら」
ところで 「面妖」 という一般的には時代劇などでもっぱら使われる言葉が当て字だったとはいえなぜ突然でてきたのか…と云えば、コミケ (第一回は 1975年12月21日 開催) が誕生してしばらくして連載を開始し、当時のマンガ ファン の男性に絶大な人気を得ていたマンガ、「うる星やつら」(高橋留美子/ 小学館/ 週刊少年サンデー/ 1978年〜1987年) が強く影響していたんだろうと考えられます。
初期の 「コミケ」 では、後の 同人誌即売会 (同人イベント) のように、同人誌の 頒布 を目的としたような集まりというよりは、マンガファンが集う交流会、肉筆回覧誌 の 展示 のような感じでしたが、後に 「創作系」 と呼ばれる 「パロディ」 や 「二次創作」 が人気となり、むしろそちらが 「同人誌」 の主流となると、必然的に ビキニ でかわいらしい 「うる星やつら」 の ヒロイン、「ラムちゃん」 がその格好のモデル、対象となり、また 「エッチな要素」 を持つようになりました。
その際、「うる星やつら」 に登場する友引高校の保健室にいる 巫女さん キャラ、サクラや、その叔父、錯乱坊のセリフとしてよく出ていた 「面妖」 が、前述した 「Men用」 や 「これまでとはちょっと違う変な本」、何より 「邪念が渦巻いておるわ!」 な本を指す言葉として使われるようになったのでしょう。 実際はもっと直接的な理由 (例えば 「うる星」 の 「FC」 関連で有力な 同人サークル が発行したエロ同人誌で、タイトルが 「面妖」 だったり、サクラさんが妖怪に襲われる筋書きで 「面妖な」 などとしゃべるなど) が発端だった可能性もあるとは思うのですが、当時の資料が見当たらず、複数の証言がある 「Men用本」 由来説以外の語源となると、探すのがちょっと困難です。
ちなみにこれらの状況や名称は、外部発表する、不特定多数に頒布するのが前提の同人誌に限ります。 自分だけ、あるいは仲間とだけ見るような個人的な回覧誌、同人誌では、当然ながらもっともっと古くから 「裸にしちゃえ」 な本はたくさんありました。 なにせ当時まだ 「コミケ」 に行っていなかった小学生〜中学生の 筆者 (ガリ版で同人誌は作っていた) ですら、ドラえもんのしずかちゃんや、ラムちゃんのエロ絵を描いて友達と見せ合いしてましたか
初期美少女同人やコスプレの土台を作り上げた 「うる星やつら」
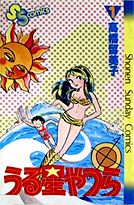 |
| うる星やつら/ 高橋留美子 |
その後 「うる星やつら」 はアニメ化され大ヒット。 「コミケ」 における 「同人誌」 の カテゴリ で最も大きな勢力となる アニパロ をも強く牽引し、さらにラムちゃんの コスプレ が 「コミケ」 などに登場。 取材に訪れた一般のマスコミなどにも取り上げられ、大きく注目されるようになりました。
結果、「こういうマンガファンの祭典が開かれている」 などとその存在を世間に広める役割を果たすなど、単に初期の同人を代表する巨大な ジャンル を作り上げた 作品 であるというだけでなく、おたく 文化のいくつかの誕生と発展に、無視できない大きな足跡を残したお化け作品ともなっています。
また 作者 の高橋留美子さんがプロデビュー前に 「コミケ」 に参加していたこと (その意味で、古めかしい 「面妖」 は 「コミケ」 や 「同人」 の世界の空気から生まれた言葉だとも云えます)、あるいは 「ラムちゃん」 のエロ同人誌に対し版元の小学館が法的な対応を検討するとの コメント を出すなど、著作権 の問題をはじめ、後に現れる同人を取り巻く様々な問題や状況をもっとも早く生じさせた、さきがけ、象徴的な作品でもあります。
さらに 「面妖本」 自体も、当時多かった 海賊版同人誌 などに頻繁に無断使用されたり、転売屋 や 同人ゴロ が暗躍する素地を作っていたなど、同人の世界そのものも、現在よりもずっとずっと アングラ な 雰囲気 だったですね。 「同人誌と云えば自販機」 などという時代もあり (「同人誌を無許可複製したエロ本が、道路沿いのエロ本の自動販売機に入っているケースもあった)、混沌とした男性向け同人の世界で脚光を浴びるヒロインが、まさに 「ラムちゃん」 でした。
「蛍ピ本」「蛍ピ必須本」 などと呼び名も
なおエロ同人誌の独特な呼び方には、面妖本や特殊同人以外にも、「蛍ピ本」「蛍ピ必須本」 なんてのもあります。 これは、肌色を美しく発色させるために使うインキ色 蛍光ピンク からきています。 また18禁本を直接指すわけではありませんが、「薄い本」 などといった表現の仕方もあります。